Ben MonderがMy Music Masterclassの教則動画(オンラインで購入可能。紹介記事)で説明していたアルペジオのフィンガリングについて書いてみます。
ベン・モンダーはこれを彼の最初の先生であるChuck Wayne(チャック・ウェイン)から習ったそうです。例えばセブンス・コードのアルペジオをどうやって弾くかという話なのですが、6弦から開始すると次の5つのパターンが考えられます。
譜面の上の数字、例えば最初の「112」というのは「最初の弦で1音、次の弦で1音、次の弦で2音弾く」ことを意味します。「121」の場合、6弦で1音弾いて、5弦で2音弾いて、4弦で1音弾く。こんなふうに、1度・3度・5度・7度のアルペジオをギターで弾く場合、「112, 121, 211, 22, 1111」という5つのパターンが考えられます(6弦からスタートした場合)。
で、上のいずれかのパターンで6弦からスタートしてセブンスコードのアルペジオを弾いたら、終着点の弦から1オクターブ上のアルペジオを新たに弾きます。この場合も、上の「112, 121, 211, 22, 1111」のいずれかを選ぶことが想定できます。しかし「1111」(1つの弦につき1音)は、弦が足らないので弾けないことがわかります。
5×5の順列組み合わせは25。しかし「1111」と「1111」の組み合わせはギターという楽器の制限上、弾けないので(7弦ギターなら弾けるのかな?)、それをマイナスすると24通りの弾き方があることになります。
ここまではアルペジオの根音形(ルート・フォーム)の話。セブンスコードには第1転回形・第2転回形・第3転回形があるので、24を4倍します。すると全ての転回形を含めるなら、「あるセブンスコードについて、2オクターブにわたるアルペジオを6弦スタートで弾く場合、24×4=96、ということで、96通りのパターンがある」ことになります。
そしてセブンスコードにはMajor 7th/6th, Minor 7th/6th, Dominant 7th, Half Diminished, Major 7th #5, Diminished 7th等々の種類があるわけで、それらを積算すると… 重複分を省いても”Art is long, life is short.”という感じです(まぁ、すぐにこれを全部やらなくても楽しめるのが音楽の良いところ)。
ベン・モンダーの面白いところは、彼のあの超絶技巧と圧倒的な創造力が、こうした本当に当たり前の地道な練習に支えられているらしいところです。彼のレッスンを受けたあるギタリストは、「私はあとどんな練習をしたらいいでしょうか」と質問したところ、「君には必要な練習方法を全て教えた。あとはそれを網羅するだけだよ」と言われて、話が終わってしまった、と言っていました。
勿論、特定のアルペジオの弾き方の組み合わせでフィンガリングが変わる場合はどうするか、上まで行ってしまった後はどうするか、という場合のTipsのようなものはモンダーの教則動画で説明されているので、英語に抵抗がない方は是非御覧ください。このアルペジオの弾き方については”Ben Monder 3″で解説されています。「ここまで弾いたら後は9thとか#11thを弾くと良いよー」みたいなナイスな内容もあります。
ベン・モンダーはこういう、それ完全にマスターするまでにヘタすると死ぬまでかかるだろう、的な練習方法をたくさん知っていて、実際に実践してきたようです。私も気長に取り組んでいますが、まあ老後にやることがなくて退屈するとかそういうことには絶対にならなそうです。
このアルペジオの練習、組み合わせによっては一気にハイポジションに飛べるものがあったり、アルペジオだけでなくスケールを重ねあわせて指板を見るようにするとかなり見通しが良くなります。時間はかかりますが、勿論メジャー以外のコードクオリティでもやります。
何か調子が悪くて練習する気になれないな、という日でも、こういう基礎練習はやればやっただけ自分のものになるのでおすすめです。


 Blackstar
Blackstar
 amorphae
amorphae
![Hydra [輸入盤]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41ibZB9nTDL._SL160_.jpg) Hydra [輸入盤]
Hydra [輸入盤]
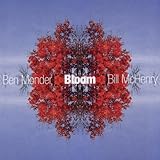 Bloom
Bloom


 KPP BEST 通常盤(先着お買い得パッケージ)
KPP BEST 通常盤(先着お買い得パッケージ)










 バッハ, J. S.: イタリア協奏曲 ヘ長調 BWV 971/ヘンレ社/原典版
バッハ, J. S.: イタリア協奏曲 ヘ長調 BWV 971/ヘンレ社/原典版
